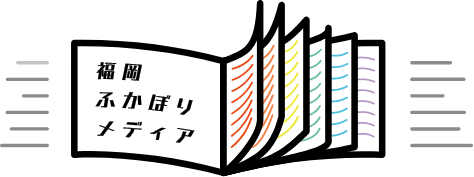ガラス張りの通路を歩きながらパンガー湾を一望できる「ビヨンド・スカイウォーク・ナンシー」
インド洋沿岸諸国に甚大な被害をもたらしたスマトラ島沖地震から20年の節目を迎える。タイでは8万人あまりが亡くなったとされ、犠牲者の多くは南部の観光地・プーケットやカオラックのあるパンガー県に集中したという。そのパンガー県周辺が今、田舎の素朴な情景と手つかずの自然が広がるリゾート地として注目されている。
市場でふれる人々の暮らし
パンガー県には、タイで最多となる六つの国立公園がある。プーケットはリゾート地として日本人にも広く知られているが、その北に位置するカオラック周辺は、欧米での知名度に比べて日本ではまだなじみが薄い。
津波被害の爪痕は今なお残っているのだろうか――。福岡空港を発ち、バンコクでの乗り継ぎを経てプーケット国際空港から車で1時間ほど。タイ国政府観光庁の案内で6月、パンガー県を訪れた。
初めての土地を知るには、地元にある市場を訪ねるのが一番。周辺でとれる果物や野菜、魚介類が並び、その歴史と風土から醸成された地域の”におい”、そこで営まれる人々の生活の”息づかい”を肌で感じられるからだ。
カオラックに着いたのは午後9時。翌朝、早起きをして、バスターミナルそばにあるボー・コー・ソー市場に足を運んだ。市場は朝5時から昼前にかけて開いており、生鮮食品から日用品まで幅広い商品を扱っている。食事ができるスペースもあった。
観光客の姿はほとんどなく、一日の始まりを迎えた住民の”鼓動”が伝わってくる。カメラを向けながら「撮ってもいい?」と表情と視線で合図すると、にっこり笑顔が返ってきた。さすがは、微笑(ほほえ)みの国――。カメラを気にすることなく、日常の時間が流れていく。人々の笑顔が市場の彩りをさらに豊かにしているようだった。
市場には、近くの寺の僧侶が買い物客らから施しを受ける姿もあった。ごはんやカレーのスープ、野菜などの食料を託し、ひざまずく人に僧侶が何かつぶやいている。地元ガイドのアヌスさん(53)に尋ねると「ねたみなどの悪い部分を出してしまって、『幸せが訪れますように』と唱えているのです」と教えてくれた。
人口の95%近くが信仰の厚い仏教徒といわれるタイ。朝の市場でその側面に触れた気がした。撮影のお礼を伝えようと僧侶に頭を下げると、黙礼を返してくれた。
アヌスさんによると、海岸から遠くないこの市場も津波で壊滅的な被害を受けたそうだ。周囲には築20年未満と思われる建物が並び、被災地の”面影”はなかった。
息をのむ天空の大パノラマ
パンガー県には、SNS上で「一生忘れられない絶景」との言葉が踊るスポットがある。2023年10月にできた「ビヨンド・スカイウォーク・ナンシー」で、最近とくに話題になっているようだ。
パンガー湾のパノラマを一望できる新しい観光ポイント。海抜80メートルの高台につくられた全長180メートルのガラスの回廊で”空中散歩”を楽しめる。森の先に見える峰々は雄大で、天に向かって優美な曲線を描く。まるで水墨画の世界のようだ。
興奮気味にスタート地点に向かうと、事前の注意事項をしっかりと伝えられる。まず滑り止めが付いたカバーを靴にかぶせる。スマートフォンの撮影で使う自撮り棒、杖(つえ)や日傘の持ち込みは禁止。雨の日にはレインコートが手渡される。強い風が吹くことがあり、安全の確保とともに、ガラス面を傷つけないためでもあるそうだ。
いざガラス面の前に立つ。500キロの重さにも十分耐えられるという1メートル四方の頑丈なガラス3層で作られ、絶対安全とは聞いたが、なかなか一歩が踏み出せない。
立ちすくんでいると、後続の人に次々と追い抜かれていく。手すりを握り、下を向かないようにして足を前に進めてみる。緊張は次第にほぐれていき、絶景に怖さを忘れて、ひたすらシャッターを押し続けた。
海で出会った初めての光景
次に向かったのは、スカイウォークからも見えたパンガー湾の島々。観光用のミニボートに乗船して、海に大きなくさびを打ち込んだような形のタプー島へ。波に浸食されながら、絶妙なバランスで立っている高さ約20メートルの不思議な造形の島だ。
映画「007/黄金銃を持つ男」のロケが行われたことから、別名「ジェームズ・ボンド島」と呼ばれ、パンガー湾観光の一番の人気スポット。そばにある小さな島に大勢の観光客が訪れ、水辺で遊んだり、土産物屋をのぞいたりしてにぎわっている。
島を離れ、マングローブ林を横目に見ながらさらに進むと、石灰岩がそそり立つパンイー島が近づいてきた。「シージプシー」と呼ばれる住民が海上に平屋建ての高床式住宅をつくり、約200世帯が水上生活を送る小さな集落がある。
島民のほとんどはイスラム教徒で、漁業や観光で生計を立てているという。集落には学校のほか、二つのサッカー場もあり、うち一つは海に浮かんでいるから驚きだ。柵はなく、ボールが海に落ちたら、そのつど泳いで取りに行くそうだ。
島の集落をぐるりと歩いてみた。貝殻で作ったアクセサリーや海産物を扱う土産物屋、生活用品を売る雑貨店が並び、その合間に住居がある。玄関も壁もなく、昼寝や食事の様子も丸見えだが、ここでも目があえば微笑みを返してくれるのがうれしい。
絵の世界!?マングローブ林
カヤックに乗ってマングローブ林を間近に見ることができるツアーにも参加した。スタート地点は400人ほどが住むバーン・ターディンデーン集落の入り江。アンダマン海に近く、20年前の津波では大きな被害を受けたという。
被災後、FAO(国連食糧農業機関)などの支援を受けて、マングローブのある海をカヤックで周遊する観光資源にし、野菜を地元で作ったドレッシングと一緒に食べ、草木染なども体験できるツアーを実現した。
被災の3年後、3隻のカヤックで始めた観光ツアーは規模を年々拡大して、今では25隻を数えるまでに。英会話ができる住民は少ないものの、飾らない実直なもてなしが「素朴で味わいがある」と、海外からの観光客に喜ばれているのだという。
カヤックの後方に年配の住民が乗り、舟を操ってくれる。小さな入り江を出発したカヤックは間もなく、マングローブの茂みの中へ滑り込んでいく。風も波もない静かな水面は、周囲の緑や木漏れ日を鏡のように映し出す。まるで印象派の油絵の中に紛れ込んだような不思議な空間だった。
この局面を写真でどのように表現できるのだろうか――。下半身が固定された狭い舟の中で、360度カメラを取り出してみたり、レンズを次々に換えてみたり、ちょっと慌ててしまった。あの情景をじっくりと堪能できなかったのが悔やまれる。
15分ほどすると林を抜け、穏やかな水面が見渡せた。手応えのある一枚が撮れたのでは――という安堵(あんど)感と頭上に広がる真っ青な空が、緊張から解放してくれたのだろう。日本では聞き慣れない鳴き声のセミがいることに、ようやく気づいた。
入り江に戻る途中、「この林にはどんな動物がいるのか」と住民に聞くと「ワニ」だという。ほかの参加者と一緒に顔をこわばらせていると、満面の笑みで「冗談よ」――。軽快な笑い声が静かな水辺に響いた。
「いのち」の旅立ちを見送る
最後に訪れたのは、1979年からウミガメを保護しているアンダマン海に面した海軍の施設。入り口には、先の津波で被災した軍艦が展示されていた。今回の旅で、この地が被災した事実を伝える数少ない遺物の一つだった。
施設では、近海の島で産卵したウミガメの卵を掘り出して孵(ふ)化させ、5か月から1年の間、大きな水槽で育てている。海軍の担当者によると、保護をしないと親ガメになるまで生き残るのは1%強に過ぎないという。
沖にたどり着く前に、捕食されたり、網に引っかかったりするからだ。施設で一定の大きさまで育てることで、放流してからの生存率は30~50%に上がったという。
滋養強壮に効果があるとされ、高値で取引されていたウミガメの卵。そのため乱獲されて生育数が減り、どう保護していくかが課題になっていた。そこで統制力のある海軍が立ち上がり、保護に乗り出したという。
この日は、手のひらサイズに育った生後5か月のウミガメを海に放つ場面に立ち会った。はじめは周囲を見回し、どうすればいいのか戸惑っているようにも見えた小さなカメたち。やがて本能に目覚めたのか、ただひたすらに波打ち際へと進んでいった。
波に押し戻されても、また海を目指す。その旅立ちを見守る人たちから「がんばれ」と声がもれた。放たれて1分もしないうちに、カメは海の中へと消えていった。
ウミガメは遠くインド洋まで泳いでいき、3年から5年おきに出産のために戻ってくるという。付近の海辺では、大きく育ったウミガメと一緒に泳ぐ特別な体験ができることもあるそうだ。
コロナ禍前の2019年には、海外から4000万人あまりの旅行客を受け入れた観光立国・タイ。2023年にタイに渡った日本人は約80万人、タイからの訪日は約100万人と、初めて逆転したという。
その背景には、タイが親日であることに加え、コロナ禍明けの日本側の受け入れ準備が早かったことや、佐賀県や福岡県などで撮影が行われた映画やドラマがタイで人気を呼び、ファンがロケ地を訪ねる「聖地巡礼」を楽しんでいることもあるようだ。
一方、日本からタイを訪れる人はリピーターが目立つそうだ。今回、タイを訪問した4日あまりの間で、出会った人や風景などを撮った写真は1万枚を軽く超えた。見返すたび、その時々のあたたかい記憶がよみがえる。
あの微笑みにまた会いたい――。その思いに導かれ、再訪する人も多いのだろう。