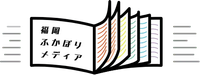ポップサーカス北九州公演を取材 出演者に熱い思いを聞いた

出演者にインタビューする学生記者たち
若い世代が記者の仕事を体験し、「福岡ふかぼりメディア ささっとー」に記事を掲載する、読売新聞西部本社の「学生記者プロジェクト」の第2弾に3人の女子学生が挑みました。今回も三好不動産(福岡市)の協力で、同社が運営する学生ボランティア支援団体「一般社団法人アースプロジェクト福岡」から3人が参加しました。3人は北九州市八幡東区で開かれている「ポップサーカス北九州公演」に足を運びました。
<バックナンバー>
▶長浜ににぎわい再び!復活した屋台街で店主さんに話を聞いた
学生記者紹介
吉田 愛(よしだ・あい)記者
映画や音楽などが大好きな福岡女子大学2年生。小学校低学年以来のサーカス鑑賞に、興奮が抑えられませんでした。
横尾 涼香(よこお・さやか)記者
黒髪のショートヘアがトレードマークの筑紫女学園大学3年生。趣味は音楽を聴くこととハンドボールです。久しぶりのサーカス鑑賞でした。
松本 由莉(まつもと・ゆり)記者
九州大学3年生。大学ではダンスサークルに所属し、エンターテインメントが大好き。人と関わることが好きな反面、一人で過ごす時間も満喫できます。
さあ、熱狂の大テントへ!
私たち学生記者は10月23日、北九州市八幡東区で開かれている「ポップサーカス北九州公演」を取材しました。コロナ禍による公演の中断期間を乗り越え、同市では5年ぶりの開催です。しなやかでダイナミックなパフォーマンスの数々に酔いしれ、感情が高ぶりました。(吉田愛、横尾涼香、松本由莉)
コミカルに観客を魅了
市制60周年と読売新聞西部本社発刊60周年を記念した公演は、「ジ アウトレット北九州」(スペースワールド跡地)に設けられた大テントが舞台です。
ショーのトップバッターとして登場したのはジャグリングの3人組でした。底抜けに明るく、コミカルな動きで観客の笑いを誘います。
軽々と技をこなしていたマルコさん(45)とカルロスさん(41)は、メキシコ出身の兄弟です。会場が盛り上がるかどうかは、最初の演目の出来が鍵を握るため、本番では常に緊張を強いられます。「それでも自分たちが誰よりも楽しむことが一番。お客さんに楽しんでもらうためには、私たちが楽しく、常に100%の力を出し切ることが大切です」。思いを体現するような躍動感に、観客のボルテージが一気に上がります。
5世代にわたるサーカス一家で育った2人。母国では就職先の一つとしてサーカスという選択肢があるそうです。活動中の米ロサンゼルスで腕を見込まれ、2004年に来日後、友人の紹介で入団しました。欠かせない日々の鍛錬も、人前での演技が大好きな2人にとっては全く苦になりません。
実は演技の直前、カルロスさんが金具で手をけがするアクシデントがありました。テーピングで応急処置を済ませ、観客に悟られないように、いつもの笑顔とテンションで演じたそうです。「『Show must go on』 何があってもショーは続けなければならないもの」。マルコさんの言葉に、高いプロ意識を感じました。
客席は一体感に包まれ、笑い声と拍手が大テントに響きます。コロナ禍がようやく静まり、公演を再開したサーカスは誰もが夢中になれる舞台を提供してくれます。
入団10年で”独り立ち”
1人乗りの「一丁ブランコ」を操るのは、たった1人の日本人団員、丹原順菜さん(28)です。体一つでブランコに座り、時に足だけでぶら下がる大技を披露すると、観客の視線がくぎ付けになります。
幼い頃から新体操を始め、高校ではダンスに打ち込みました。高校3年の進路を決める時期に、世界的なパフォーマンス集団「シルク・ドゥ・ソレイユ」の公演に魅せられ、この道に進むことを決めました。「両親や友人は驚きましたが、最終的に背中を押してくれました」
入団後は、裏方の業務をこなしながら、体幹トレーニングや空中ブランコなどの基礎練習といった地道な努力を重ねてきました。2019年から一丁ブランコの練習を本格的に始め、入団10年を経た今年2月に単独演目で念願のデビューを飾りました。
しかし、コロナ禍に直面した丹原さんの心は揺れました。「公演をいつ再開できるか分からず、目標設定が難しかったです。長引きそうだったので、一から練習し直しました」と振り返ります。練習に集中できない時やけがに苦しむと、身近にいる仲間の演技を見て、モチベーションの維持に努めたそうです。
多いときは1日3回の公演をこなすハードな日々が続きます。心身のコンディションに合わせて、練習の加減や休息を心がけるといいます。ストレスで体重が増減することもあり、「それをため込まないことが秘けつ」と明かしてくれました。
これからの目標を尋ねると、「自分で新しい技を考えたり、映像を参考にしたりして、よりレベルアップしたい」と、意欲的な答えが返ってきました。
肉体のパフォーマンス
民族調の衣装をまとった男性7人が舞台に登場しました。「アフリカンハンドボルテージ」というパフォーマンスは、道具を一切使わず、肉体だけで勝負するダイナミックさが売り物です。チアリーディングをより力強くした演技を想像してもらうと分かりやすいかもしれません。
軽やかな跳躍と、それを支えるたくましい男たち。土台になる1人の肩にパフォーマーが次々と跳び上がり、ピタリと静止する技を目の当たりにすると、けがをしないかハラハラさせられます。
サラハリディン・モハメド・フィタさん(28)はエチオピア出身で、メンバーも母国の仲間です。サーカス団員になるための学校を出て、10年前から演技に取り組んでいます。怖くないのかと聞くと、「何年もやっているから慣れたもの。高くなればバランスを取りづらいけれど、経験を積むと乗る人が増えても重さはそれほど気にならないよ」と、説明してくれました。
ふるさとの冬は短く、あまり寒くないため、「日本の冬が新鮮。食事では牛丼や味噌(みそ)汁がおいしい」と異国の印象を語ります。「体さえあれば、何でもできることをパフォーマンスを通じて伝えたい」。そう言うと、終演後に欠かさない練習に戻りました。
リボンアクロバットやフィナーレを飾るショーの華・空中ブランコに至るまでの約2時間が瞬く間に過ぎました。拍手や合いの手を観客に求めたり、客をステージに上げたりして、盛り上げてくれたサーカスの世界を体感して、しばらくは興奮が冷めませんでした。
インタビューを終えた私たちもジャグリングの基本技に挑みました。ところが、ボウリングのピンに似たクラブをたった1本扱うだけでも悪戦苦闘です。自由自在に操る陽気なパフォーマー、アスリートのような訓練を積んだ団員の皆さんの演技には、脱帽するしかありません。
北九州公演は12月10日まで続きます。皆さんも夢のようなポップサーカスの楽しさをぜひ体験してみてください。
■取材後記

横尾 涼香記者
活動を通して、取材や記事作成の難しさと楽しさを体験することができました。読む人に、どれだけ分かりやすく簡潔に伝えられるかを意識しながら書くことが難しかったです。これからの大学生活に今回の経験を活かしていきたいです。

松本 由莉記者
幼い頃に祖父母とサーカスを鑑賞した記憶が多少残っていましたが、想像以上にダイナミックかつ繊細で、ドキドキとワクワク感が最後まで止まりませんでした。私自身、パフォーマンスを見て、人間の可能性について感じさせられました。