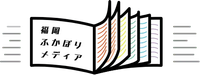西日本新聞「あなたの特命取材班」で表明した『読者とつながる』【世界報道自由デー 特別インタビュー】

西日本新聞「あなたの特命取材班」公式サイト
記事 INDEX
- お手本は「探偵!ナイトスクープ」
- LINEの投稿にはすべて返信
- 必要とされる「報道インフラ」に
読者から届いた疑問や質問を記者が取材し、社会の課題解決を目指す双方向型の調査報道「あなたの特命取材班(あな特)」。福岡市に本社を置く西日本新聞社が2018年に始め、今では地方の新聞社やテレビ局など29媒体に連携が広がっています。投稿を受け付けるLINEの登録数は1万9000人を超え、約1万5000件の疑問や質問、情報が寄せられました。驚くことに記者たちは投稿された全メッセージに返信しているといいます。これまで600本を超える記事が掲載され、記事を配信したヤフーニュースでの閲覧は約4億ページビュー(PV)に上ります。あな特が目指す読者と新聞社の関係とは。あな特の仕掛け人で、西日本新聞中国総局の坂本信博記者に聞きました。
※この記事は、国連が定めた「世界報道自由デー」(5月3日)に合わせた特別インタビュー記事です。
坂本信博さん

マレーシアの邦字紙記者、商社勤務を経て1999年に西日本新聞社に入社。長崎総局や社会部、東京支社報道部、クロスメディア報道部などを経て中国総局長。医療や教育、子どもの貧困、外国人労働者をめぐる問題などを取材し、調査報道に従事。
お手本は「探偵!ナイトスクープ」
――「あなたの特命取材班」が生まれたきっかけを教えてください。
西日本新聞には以前、「社会部110番」という名物企画がありました。専用電話で読者から疑問や相談を受け付け、記者が読者に代わって取材して記事にするというものです。とてもやりがいのある企画でしたが、長電話になることもありますし、相談が30本あっても記事になるのは1本くらいという効率の悪さは否めませんでした。記者の負担が大きいということで、企画自体もなくなってしまいました。
編集局へ直接かかっていた読者からの電話も、その後はコールセンターに集約されるようになりました。記者の負担は減りましたが、読者の生の声が届きにくくなったのも事実です。そういった電話では、記事への賛意や応援だけでなく、批判や叱咤激励もたくさんいただいていました。自分が書いた記事が読者に刺さっているのか、読者が見えづらくなり、手応えを感じられなくなっていきました。
当時のような読者とのやり取りを復活させたい。電話がSNSに変わり、2018年1月に「あなたの特命取材班」がスタートしました。
――意識したことは。
企画の参考にしたのが、視聴者参加型の人気長寿番組「探偵!ナイトスクープ」(ABCテレビ)ですね。すごく好きな番組で、新聞社のジャーナリズムとして成立するんじゃないかと考えました。読者からの取材依頼を受け、番組のように取材の過程もつまびらかにする。白黒つかないグレーゾーンの話題も果敢に取り上げ、結論は別にして「取材してみたらこうでした」と素直に書くようにしました。
こういった「あな特」の記事スタイルは、インターネットメディアと近いです。ネットニュースは滞在時間を長くし、クリック率を上げてサイト内の回遊性を高めることが重視されます。新聞記事は結論ありきで構成されますが、最後まで読んでみたいと思わせる「探偵!ナイトスクープ」的手法がネットとの親和性を高めています。
――情報提供ツールにLINEを選んだ理由は。
当初は疑問や質問が集まらないのではと不安でした。蓋を開けてみると、投稿が次々と送られてきて驚きました。インターネットが普及して社会の情報化が進んでいるのに、相談先がなくて悩んでいる人が多いことに気づかされました。
投稿が集まるにつれ、読者は新聞社にさほど距離を感じておらず、我々の方が読者から離れていっただけだと知りました。自分たちが知らせたい、知るべきだというニュースに重きを置きすぎたあまり、読者の「知りたい」を軽視していました。
読者から遠く離れたところで、私たちは仕事をしていたようです。「あなたの特命取材班」という名称もそうで、企画段階では「社会部110番 NEO」という仮タイトルをつけていました。ウェブのアナリストから「若い人は『社会部』なんて言葉を知りませんよ」と指摘され、新聞社という狭い世界の常識を読者に押しつけようとしていたと反省しました。
編集部注:LINE利用者情報が中国企業から閲覧可能だった問題を受け、西日本新聞社はLINE広報から「あなたの特命取材班」の情報提供窓口として使用しているLINE公式アカウントについては、個人情報や会話内容は「中国からのアクセスの対象外」と回答を得たという。3月18日付の西日本新聞朝刊に掲載した。
届いた投稿には記者がすべて返信
――どのようなルールで運営していますか。
同僚たちと「特ダネが手に入る便利な道具」には絶対にしてはならないと言い続けています。「かんぽ生命の不正販売問題」「愛知県知事リコール問題」など、特ダネにつながる情報が次々に入ってくるようになりました。しかし、「あな特」は情報を集めるための便利な道具ではなく、読者とつながり、読者からの信頼を得るツールだと徹底しています。
そういった理由で、LINEで届いた投稿にはすべて返信しています。
――すべての投稿に、ですか。
スタート当初は担当記者が15人いて、その日の午前中の当番が返信するルールにしていました。LINEは投稿を見ると「既読」がつくじゃないですか。返信しないと無視しているようになるので、返信せざるを得ない気持ちになります。事前に「全ての投稿にお答えできるわけではありません」とただし書きは添えているのですが、せっかく投稿してくれた人に申し訳ないので、すべてに返信するようにしています。
大変ではありますが、丁寧に返信したから読者の信頼を得られ、対面取材では話しづらいセンシティブな告発であっても、相談していただけるようになりました。
投稿が取材され、記事になった方は私たちのファンになってくれます。私たちがお願いするアンケートに率先して回答し、電話取材にも応じてくれます。場合によっては、事件や災害の画像や動画を送って一緒に報道を支える協力者にもなってくれます。ですから、私たちはLINEの登録者を「あな特 通信員」と呼ぶようにしています。
――投稿が増えると大変ですね。
そうですね。「パンドラの箱」を開けちゃったかなと思うときはありました。しかし、最もやってはいけないことは途中で放り出すこと。やり始めたらやめられない企画だということは覚悟していました。
私が土日もずっとLINEに返信していたら、家族から"LINE禁止令"を言い渡されたこともありました。「何かを犠牲にしないといい企画はできない」。そう自分に言い聞かせて、LINEに届くメッセージを見て自分を励ましてきました。
社内では当初「読者から取材のネタが提供されるので、記者の取材力が弱くなる」という否定的な意見もありました。ただ、取材の端緒がSNSというだけで、証拠を得るために現場に足を運び、人に会って話を聞き、資料を探し出して調べるという取材は、従来の調査報道と同じです。楽をしているわけではありません。
社会部110番の頃は投稿30本につき1本くらいが記事になるかどうかでした。「あな特」では半分以上がきちんと取材すれば記事になるような情報が集まります。半年ほどで初期メンバーだけでは手が回らなくなったので、編集局全体の企画に格上げされ、担当の垣根を取っ払いました。
記者たちの意識に変化が
――取り上げるテーマにルールはありますか。
それまで紙面では取り上げてこなかったテーマにも目を向け、「誰かの困りごとが、他の誰かにも共通するか」を掲載基準の一つにしています。
結論が出ないニュースを取り上げることに新聞は消極的です。法律に違反しているとか、「世界初」「日本初」とか、明確なニュース性を重視します。逆に、白黒つかないこと、結論が出ないことはとりあえず記事にしないというのが、なんとなくの慣習になっていました。
「あな特」はそういったグレーゾーンに切り込んでいきました。分からないなら分からないなりに、取材過程を含めて「ここまで調べてこうでした」という事実を読者に伝えました。さらに読者から反響があれば、追加取材をして深掘りしていくようにしています。新聞社側で記事を完結させるのではなく、読者を信頼し、読者と一緒につくっていく調査報道だと考えています。
★「ツーブロック禁止」3割
— あなたの特命取材班/西日本新聞社会部 (@nishinippon_sha) July 14, 2020
福岡県立の高校・中等教育学校全95校の校則を調べたところ、少なくとも約3割の27校が禁止項目に明記していた。https://t.co/7bp1E9RJo3#西日本新聞
――記者の意識に変化はありましたか。
社会から頼りにされ、自分たちにしかできない社会の役割があるんだと、やりがいを感じています。LINEの投稿は編集局の記者なら誰でも見られます。取材するのは挙手制で、早い者勝ちです。ニュースの価値判断はそれぞれの記者に委ねています。自分がニュースだと思わなかった投稿なのに読者の反響は大きかったなど、記者たちは自分のニュース感覚が社会とずれていないかを問い直すきっかけにもなりました。
読者からの投稿は疑問や質問だけではありません。記事の感想も届くので、記者のモチベーションアップにつながっています。
Yahoo!ニュースで累計4億PV
――読者の反響はいかがでしたか。
これまでに掲載した記事は600本を超えました。単純計算で3日に1本は掲載されています。新型コロナウイルスが拡大してからは、新型コロナ情報に特化した企画など、スピンオフ企画も生まれています。
LINEの登録者数は約1万9000人で、これまでに受け取った投稿は1万5000件に上ります。ヤフーニュースに配信した記事は累積で4億PVを記録しました。今まで最も多く読まれたのは「記者が迷惑メールにマジレス(まじめに返信)してみた」という記事で、発行部数をはるかに上回る数字を記録しました。
そういった「数字」が出たことで、「あな特」への社内の評価も徐々に変化していきました。「PV至上主義」に陥ってはならないという気持ちを持っていますが、手応えを得る上で大切な指標でもありますね。
#迷惑メール を追う第2弾は「迷惑メールにマジレスしてみた」。特命取材班が返信すると「私、優子」と即レスがー。新手の #架空請求 をしてきた業者とも「対決」しました。#西日本新聞 #あなたの特命取材班 #news #スクープ #モデル #アイドル #金 #質問 #プロフ #コンビニhttps://t.co/lE7RGmUyAG
— あなたの特命取材班/西日本新聞社会部 (@nishinippon_sha) February 17, 2018
――「数字」以外に手応えを感じたことは。
アンケートの返答率は高いときで1~2割に達します。世論調査とは異なりますが、1000~2000人規模の読者の声が届きます。以前は天神に出て通行人のコメントを拾うという取材をしていましたが、書き手の意思に沿って原稿ができあがってしまうことも実際にはありました。
取材の手法が今までとはまるで変わりました。こちらで想定した回答を記事に当てはめていく「作業」ではなく、こちらの想定を超える声が届くようになり、読み応えのある記事ができるようになっていきました。
国内だけでなく、海外からも相談が届きます。新型コロナの感染が拡大した際、日本に永住権を持つペルー国籍の学生から寄せられた相談は、日本政府のチャーター機に搭乗できずに困っているというSOSでした。「あな特」での報道を受け、永住者の入国が緩和され、学生の帰国が果たせたこともありました。
今朝、西日本新聞 #あなたの特命取材班 に、南米ペルーにいる早稲田大学の男子学生からSOSが届きました。研究のために現地を訪れていたものの、新型コロナウイルス禍で国境が封鎖され、日本に帰国できなくなっているといいます。記者がさっそく取材しました。https://t.co/GSQiRUSfkc#緊急事態宣言
— あなたの特命取材班/西日本新聞社会部 (@nishinippon_sha) March 26, 2020
「あな特に相談してみたら」の声に手応え
――ネットでは「オワコン」「マスゴミ」など、新聞不要論も散見されます。「あな特」はそういった批判への新聞社側の回答でもありますね。
私の妻はおもちゃ屋を経営しているのですが、店番をしていたら、来店した小学生の親御さんたちが「最近、困ったことがあってね」みたいな会話をしていたそうです。小学生の男の子が「『あな特』に相談してみたら」と言うので、妻がびっくりして聞くと、小学校の授業で「子どもホットライン24」などと一緒に、困ったときの相談先として「あな特」が紹介されたそうです。その話を妻に聞いたとき、「あな特」が社会のインフラとして浸透しつつあるんだと、勇気がわいてきました。
――社会に貢献できていることへの「実感」。記者としての大事なモチベーションですね。
そうです。私を含めて、社会に役立ちたいと思って記者を志した人がほとんどです。困っている人を助けたいとか、世の中を少しでも良くしたいとか。多くの仲間の知恵の結晶として「あな特」が生まれ、実際に「相談してみたら」と言っていただけるところまで至りました。
影響力も感じています。取材先では、以前より新聞が軽んじられていると、ひしひし感じていました。それが「あな特ですか?」と聞かれるようになり、新聞社は怖くなくても、新聞を支える有権者や納税者、消費者を、行政や企業は無視できません。読者と強く結びつくことで、新聞社が持っていた「迫力」を取り戻せつつあります。
しかし、それを我々が勘違いして「自分たちが偉くて、価値判断するのは自分たちだ」とおごり高ぶってしまえば、読者の信頼を失います。特ダネが手に入る便利な道具には絶対にしない。読者とつながるツールだと、ことあるごとに振り返るようにしています。
――読者の「知りたい」に応えるのは新聞社の原点なのかもしれませんね。
西日本新聞は創立144年になります。創刊号は西郷隆盛が率いる明治政府に反対する士族が反乱を起こし、熊本あたりにまで北上しているという内容です。福岡が戦渦に巻き込まれるか心配だから戦況を知りたいという声を受け、西南戦争の現場をリポートしたのです。命がけで取材をして報告したら、読者が喜んで読んでくれた。「あな特」がやっていることと同じで、現代はデジタルの力を借りて、当時より取材や表現の可能性が増えています。
全国へ広がるローカルメディアのパートナー
――「あな特」は全国の報道機関でも取り入れられています。
西日本新聞には「西日本問題」というのがあってですね、社名は「西日本新聞」と大風呂敷を広げていますが、福岡を中心に九州エリアで発行している新聞です。関西から情報提供してくれた方がいたのですが、「九州の新聞でして……」とお断りの連絡を入れたら、「おたく"西日本"ちゃうの」とお叱りを受けたことがありました。
読者の信頼が高まっているのに、読者を裏切ることになる。そう考えて、同じ志を持つ地方紙とも情報を共有して、ともに調査報道に取り組もうとスタートしたのが「ジャーナリズム・オン・デマンド(JOD)」です。2018年9月から東京新聞と琉球新報がパートナーに加わり、今では29媒体にパートナーが広がっています。
――パートナー各社とはどのような連携をしているのですか。
新聞発行エリア外からの調査依頼は、情報提供者が同意した場合に限って、パートナーと情報共有しています。JODパートナーシップには「ノウハウの共有」「ネタの共有」「コンテンツの共有」という三つの柱があります。パートナーが紙面やウェブサイトで掲載した記事を、弊社の紙面で使用することもあります。これまではブロック紙3社連合(西日本新聞社、中日新聞社、北海道新聞社の連携)や災害報道などの特別な場合を除いて、地方紙の記事の共有はありませんでした。そういった意味でも画期的な取り組みになっています。
――コロナ禍での連携はありますか。
あります。新型コロナ禍が深刻化するにつれ、LINEへの投稿数は増えました。多くの方が不安に思っていて、初期の頃だと「マスクでウイルスが防げるのか」といった質問がありました。記者は対面取材が制限されるという初めての経験をしました。そこでもLINEで読者とつながっていたことが武器になりました。新型コロナの問題は、福岡であっても東京であっても、課題や問題に差はありません。新型コロナ関連の情報はJOD加盟社で積極的に共有しています。医療専門家へ取材した記事を融通しあったほか、デマ情報が拡散したときも連携して沈静化に向けた報道を行いました。
熊本に続き、福岡でもトイレットペーパーの品切れが続出しています。新型コロナウイルスで「マスクの材料に紙が回されるので不足する」「中国から原材料を輸入できなくなる」というのは完全なデマです。業界団体は「在庫は十分ある」と強調しています。#あなたの特命取材班https://t.co/SLdGOMKaqu
— あなたの特命取材班/西日本新聞社会部 (@nishinippon_sha) February 28, 2020
社会に必要とされる「インフラ」として
――「あな特」のような調査報道を続けるためのマネタイズについてはどのように取り組んでいますか。
「あな特」の記事に関してはネットで無料公開しています。なぜかというと、読者と一緒につくった記事だからです。西日本新聞のブランド価値を高め、ファンを増やすのが目的なので、現在は有料化を考えていません。
JODを始めるときは「フランチャイズ制を導入して加盟料を徴収しては」という意見もありましたが、加盟料などはいただいていません。「LINEの返信はどうしたらいいか」など、ノウハウを含めてすべて共有しています。フランチャイズ制を導入していたら、多少なりのお金は稼げたかもしれません。しかし、今のような大きなうねりにはならなかったでしょう。西日本新聞もパートナーから学んでいます。パートナーの取り組みに刺激を受け、「あな特」を再構築したことが何度もありました。
発行部数の減少にともない新聞社の経営が厳しくなり、西日本新聞は危機感の強さだけなら日本一だと思っています。ですから、新しいことに挑戦していこうという雰囲気は強いです。読者が知りたいこと、困っていることに向き合い、読者の協力も得ながら地域の課題を解決する調査報道をしていくことで、社会の「インフラ」としての地位を確保し、生き残っていけると考えています。「あな特」が目指すジャーナリズムは、社会や地域に必要とされる「インフラ」であり続けることです。
――「読者」の知りたいに応え続ける?
報道機関が「知らせたい」「知るべきだ」と考えているニュースがある一方で、読者が「知りたい」と思っているニュースもあります。新聞を支えてくださっている読者の「知りたい」に応えることを、今までの我々は軽んじていたのではないか。もちろん「知らせたい」「知るべきだ」というニュースは大切です。読者の「知りたい」も大切に、ニュース量全体のバランスをとっていこうという考え方です。
――報道現場を支える記者の存在も重要です。
新聞の発行部数が減り続け、読者が高齢化していくと、私たちは「オワコン」「マスゴミ」と揶揄(やゆ)されるようになりました。将来を悲観した若い記者は次々と全国紙やテレビ局に転職していきました。それが今、首都圏でも「あな特」の知名度は高く、「あな特」で関心を持ってインターンや説明会に参加してくれる学生が相当数いると聞いています。「読者離れ」だけでなく、報道の未来を支える若者たちの「記者離れ」も食い止めたいのです。
「あな特」が目指す調査報道とは
――新聞の未来をどのように考えていますか。
私が入社した当時は「ネットなんか取材に使うな」と言われた時代です。今では考えられませんよね。SNSで読者とつながって、読者の「知りたい」に応えていこうという理念が、最近ようやく社内に浸透してきたかなと感じています。
自腹営業や不正営業に苦悩する全国の郵便局員さんと #あなたの特命取材班 でつながった1人の社会部記者の調査報道が、石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞に選ばれました。
— 坂本 信博/Nobuhiro SAKAMOTO (@SaidaniQ) February 17, 2021
読者とのキャッチボールで展開された調査報道が評価され、嬉しい限りです。#あな特#西日本新聞https://t.co/rUpYZVGsoz
西日本新聞は九州の地方紙ですが、国内では東京、海外だと中国や韓国、アメリカ、タイにも取材拠点があります。ローカルでありグローバルでもある「グローカル」メディアなんだと、意識しています。ベランダでタバコを吸う「ホタル族」に困っているという相談は福岡の通信員からでしたが、ウェブに記事を公開したら全国から反響がありました。それまで「それって九州の話なの?」「九州に関係者はいるの?」と、九州にこだわり過ぎていたところがありました。でもそれは新聞社側の論理でした。ローカルメディアとして地域に根ざすことを基本にしつつ、視点を変えれば日本中で読まれるし、言葉の壁さえなければ世界でも読まれると思っています。
「あな特」に限らず、読者の「知りたい」に応える調査報道は大切だと考えています。読者の声に耳を傾け、読者の代わりに時間と体力と頭を使って応えていくのは、新聞記者にしかできないことではないでしょうか。新聞社として、読者に必要とされ、世のため人のためになること。それがなくなると報道機関としての存在意義はありません。必要とされるインフラになれば収益もついてきます。読者の知りたいに応えていくことが記者の役割で、私たちにしかできないことであるはずです。