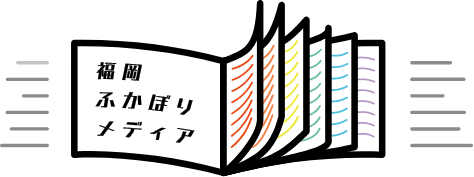【長崎】炭鉱の味・池島「かあちゃんの店」が閉店へ
九州最後の炭鉱があった長崎市の離島・池島に、炭鉱マンの寮の食事担当だった女性が閉山後に開いた島唯一の食堂がある。「かあちゃんの店」の名で親しまれた店は3月末、老朽化した施設の解体を前に19年の歴史を閉じる。常連たちは島の活気を支えてきた「かあちゃん」に、感謝の思いを抱いている。
胃袋支えた
店の主は島民の脇山鈴子さん(84)。長崎県佐世保市出身で、20歳代半ばの頃、夫(故人)と幼い子ども2人の4人で池島に移り住み、夫は炭鉱関連などの仕事に就いた。
当時は操業開始間もない時期。男たちは、日本の高度経済成長を支え、「黒ダイヤ」と呼ばれた石炭を無心に掘り続けた。脇山さんが従事したのは、炭鉱マンたちの寮の食事担当だった。朝昼晩の食事をつくって、体力を要する男たちの胃袋を支えた。
面倒見のいい脇山さんを炭鉱マンたちは慕い、自宅にもたびたび訪ねてきた。長女・利恵さん(60)は「時には10人以上が来て、足の踏み場もないほど。あの頃、島は活気にあふれていた」と懐かしむ。
しかし、燃料の石油への転換に伴い全国の炭鉱が次々と閉山。九州で最後まで残った池島炭鉱も2001年11月に42年の歴史に幕を下ろした。職場をなくした島民の多くは島を去り、活気はみるみる失われた。
壁にびっしり
寂れる島を守りたいと、脇山さんは2004年に食堂を始めた。店を構えたのは、島中心部の市設池島総合食料品小売センターの一角。近くには炭鉱マンが暮らした8階建て住宅の廃虚があり、最盛期には多くの買い物客でにぎわった場所だ。
「残った高齢者や来島者たちが、ご飯を食べてくつろげる場所を」。そんな思いだった。店名は、炭鉱マンたちが「かあちゃん」と慕う様子を間近に見てきた利恵さんが付けた。
店では、寮で鍛えた料理の腕を存分に振るった。カツ丼やオムライスなどの定番、長崎名物・トルコライスのように1皿にスパゲティ、カツ、チャーハンを盛りつけた料理――。どれもボリューム満点だ。
中でも人気なのは、自家製豚骨スープで作る具材たっぷりのちゃんぽん。「お客さんが来るかも」と盆も正月もほぼ毎日店を開け、その味と変わらぬ笑顔で、住民や「里帰り」した元島民の心を温めてきた。「ありがとう!かあちゃんのみせ」「ちゃんぽん最高」「いつまでもお元気で」――。年季の入った店の壁は、客が書き残したメッセージでびっしりと埋まっている。
時の流れ
老朽化したセンターの取り壊しが決まり、自身も高齢のため閉店を決断した。病気とは無縁だった脇山さんだが、今年に入ってめまいなどの症状に悩まされ、1月上旬から1か月ほど休業した。2月中旬から「お客さんに申し訳ない」と再び厨房(ちゅうぼう)に立ち、最後の日となる3月31日も、いつも通り午後6時頃まで店を開けるつもりだ。
10年ほど前から常連の島民・森洋子さん(61)は「おいしいご飯だけじゃない。悩みを打ち明けた時も『大丈夫よ』と笑い飛ばしてくれた。かあちゃんは心のよりどころだった」と閉店を惜しみ、「『ありがとう。お疲れさま』と言いたい」と感謝を口にした。
人口は閉山時の2713人から103人(3月1日現在)にまで減り、高齢化率は6割を超える。「炭鉱が閉山したように、いつか終わりがくるのは仕方なか。時の流れには逆らえん」と、脇山さんは言う。それでも、娘の利恵さんは「食堂は母の生きがいだった。本当によく働いた」と、長年の苦労をねぎらう。
「生涯、この島で暮らせるように、元気でおらんばね」。島の姿が変わっても、島を愛する「かあちゃん」の思いは変わらない。
「第二の軍艦島」
池島は長崎市西部の約7キロ沖に浮かぶ周囲約4キロの離島だ。海底炭鉱の旧池島炭鉱は1959年に営業出炭を開始。70年には労働者ら約7700人が生活し、最盛期の85年には年間約150万トンの出炭を誇った。
閉山後は人口流出が進み、炭鉱跡を活用した観光地化の模索が続く。古びたアパート群は人気で、2015年に世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」に登録された同市の端島炭坑(軍艦島)にちなんで「第二の軍艦島」とも呼ばれる。
長崎市などは11年度から、島に残った元炭鉱マンが坑道を案内する「炭鉱体験ツアー」を始めた。市によると、コロナ禍前の15年度のツアー客は約7400人。20~21年度は落ち込んだが、22年度は約3300人(見込み)に回復している。