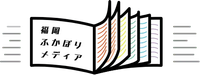和と洋が出会う器をめざして 「小石原焼」の職人が続ける模索と挑戦
同じ繰り返しでいいの?
小石原地区に60~80人いるとされる職人の一人、「まるた窯元」の太田剛速さんは、変化する生活様式に合う作品を目指して試行錯誤を重ねている。
「食生活は変わっていく。40年前と同じものを作っているだけではいけない」。その一方で、「この土地の素材を使い、ここでしかできないものを作りたい」とも。和食だけでなく、洋食にも合うデザイン。それを考える毎日だ。
窯元の家に生まれた太田さんだが、陶芸の道を強く意識したことはなかったという。しかし、親の背中を見て育ったからか、造形分野の大学に進むと、そこで創作意欲に火が付いた。
卒業後は、実家と別の窯元で3年間修業した。朝から晩まで土に向かう日々の中、胸の奥に引っかかる思いがあった。「ずっと同じことの繰り返しでいいのか?」。自問自答を続け、26歳のときに答えを求めてヨーロッパへ渡った。
日常の営みを世界が評価
渡航の理由の一つは、イギリスの陶芸家バーナード・リーチについて学ぶこと。その流れをくむイギリスの窯元やスペインで研修し、日本と欧米との違いを体感した。
「欧米は形のいびつさもアートとして楽しむ。一つひとつの形が微妙に違い、全てが一点もの。日本はその逆で、同じ形のものを多く作ることに長けている」と話す。
自身の作品を披露する機会もあった。独創性を打ち出した力作は通用せず、意外にも小石原焼の技法が評価された。「欧米では技を受け継ぐという文化が根付いていないように感じた。『作り手への尊敬の念』も日本の方が強かった」と振り返る。
「新しいものを求めて日本を出たが、結局、毎日やっていたことが世界で通用するのだと痛感した」。それでも「昔のままではいけない」という思いが消えることはなく、小石原の伝統を生かしたアート作品にも挑み、国内外の展覧会で受賞を重ねた。
和と洋の出会いを求めて
日用雑器の制作では、海外での経験が生きている。洋食はプレート状の皿にいくつもの料理を載せることが多いが、和食は皿を使い分ける。さらに、手に取って使われる和食器は、持ち上げやすい「深さ」が重要になる。
小石原焼のプレートは人気を呼び、多くの窯元で同様のものが制作されるように。「和と洋の両方に合うためには、大きさや色合いをよく計算しないといけない。職人は使う人の期待に応えなければ」。新しい提案に向け、アイデアを巡らせる毎日だ。
小石原焼はどうなるのか。そんなテーマにも思いを寄せる。「飛び鉋は100年くらい変わらないデザイン。消費者の選択によっては消えていくかもしれないが、そうならないようにデザインするのが職人のセンスと技なんです」。模索と挑戦が続く。