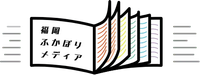五・七・五でにぎわいを! 小倉・京町銀天街を照らすユニーク川柳

ウィットに富んだ川柳が並ぶ京町銀天街
記事 INDEX
「川柳通り」の名で親しまれる北九州市小倉北区の京町銀天街。紫川に架かる常盤橋から東に約200メートルにわたって30店あまりが軒を連ねるこの商店街には、大小のパネルに筆書きされた20句ほどが飾られている。
見上げる川柳 あふれる人情
《肌荒れをさせたマスクで荒れ隠し》《ネットでは買えぬ温(ぬく)もり商店街》――。アーケード街に足を踏み入れると、天井や柱に掲げられたユニークな川柳の数々が目に飛び込んできた。京町銀天街協同組合が2003年に始めた川柳コンテストの優秀作。毎回、全国から2000~3000点が寄せられ、作品は隔月で掛け替えられる。
「寂しくて暗かった商店街を、人情あふれる明るい街にしたかった」と協同組合の理事長・辻利之さんは振り返る。商店街で老舗の茶舗を経営する辻さんが、組合理事長に就任したのは20年ほど前。国内は不況が続いており、人通りはまばらで、多くの店がシャッターを閉めていた。
当時は商店街に暴力団の事務所があり、路上にはスモークガラスに覆われた車がとまっていた。事務所の退去に向けて活動していた辻さんの店に車が突っ込む事件も起き、街には殺伐とした空気が漂っていた。
「心が豊かになる文化的な催しが必要」。辻さんは、妻の友人で「お鶴(つう)」の雅号を持つ地元の川柳作家・唐鎌美鶴さんらに声をかけ、川柳でまちづくりに取り組むことを決めた。
おうち時間で?応募が急増
川柳に着目したのは、短文でわかりやすく、歩きながら眺めてもらうのに適していると考えたからだ。当初はほとんど反響がなかったが、3年ほどすると、商店主や買い物客から「次はいつ、新しい句が見られる?」などと聞かれるようになった。
「企画は継続することが大事。続けるからこそ、人を引きつけるパワーが出てくる」と話すのは、川柳コンテストの審査委員の一人、松岡忠夫さんだ。井筒屋に長年勤めた後、クラフト作家として独立した。若い頃に大阪のデザイン会社で看板の文字を書く仕事をしていた経験を生かし、作品を清書している。
《ディスタンス取れど人情密な店》など、最近は新型コロナウイルスに関する投句が目立つ。その時々の世相を映し出す句を、独特の丸みのある文字でしたためる。
昨年度は、コロナ禍により自宅で過ごす時間が増えたこともあってか、例年を1万句ほど上回る約2万9000句が寄せられた。「お鶴さんがいないと始まっていなかった」と松岡さんは力を込める。審査委員長を務める唐鎌さんのことだ。
つながる心が街を明るく!
「川柳は、人の共感を呼び、『私だけじゃないんだ』とほっとさせる力がある」と唐鎌さんは言う。「人に喜んでもらえると作者もうれしい。作品を介して、作者と見る人たちとの間で元気が行き来するんです」
松山市生まれ、北九州市育ち。大学を卒業後、結婚し、専業主婦として約20年、家事と育児にいそしんだ。家にいることが多かったためか、気持ちが落ち込むこともあり、心配した友人に川柳を勧められた。40歳を過ぎた頃、ラジオ番組に投稿した《東大か夢ふくらむも5才まで》という句が紹介され、のめり込んだ。
審査委員長を引き受けたのは、「街を明るくしたい」という商店主たちの思いに共感したからだ。審査会では、わかりやすさや楽しさなどを基準に優秀作を選ぶ。学校や高齢者施設からまとめて送られてくることもあり、回を重ねるごとに、レベルは上がっているという。
京町銀天街には4年前、地元ゆかりの文学者を紹介する「北九州文学サロン」が開館。川柳の活動も相まって、「文学の街」としての存在感を高めつつあり、かつての暗い雰囲気はない。高く掲げられた川柳が、行き交う人々の心を今日も温めている。