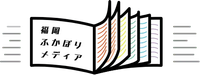あの時代に戻らないように 床下の防空壕が伝える戦禍の記憶

町家の地下に残る防空壕から天を見上げる
記事 INDEX
- 博多の町家に残る空間
- 消えゆく歴史の”証人”
- 小中学生が平和を学ぶ
太平洋戦争の開戦から82年――。戦争の体験を語り継ぐ人は年を追うごとに少なくなり、昔ながらの町並みが消えた市街地でその痕跡を見つけるのも困難になった。福岡市博多区大博町にある築約130年の町家「立石ガクブチ店」には、戦時中に掘られた防空壕(ごう)が床下に残り、戦禍の記憶を今に伝えている。
博多の町家に残る空間
1921年(大正10年)に創業した老舗額縁店の3代目店主・立石武泰さん(71)は「戦争で何が起きたのかを肌で感じてほしい」と、自宅兼店舗の地下にある防空壕を公開して、妻の陽子さん(71)とともに平和の尊さを説いている。
店はかつて大浜地区とよばれた一帯に立つ。建物の前は、江戸時代には船問屋が並んだ博多のメインストリート。現在も歴史的な遺産や文化が継承され、毎年8月に行われる伝統行事「大濱流灌頂(ながれかんじょう)」では、大灯籠に明かりがともされ、通りは大勢の人でにぎわう。
立石さんの祖父で、店を開いた安兵衛さんらが家族総出で造った防空壕。国からの突然の命令を受け、寝る間を惜しんでスコップで掘り進めたという。9か月をかけて完成した壕の内部は、広さ8畳、高さ1.6メートルほど。家族3人が身を隠すにはやや大きいが、逃げ遅れた人を受け入れられるようにとの配慮もあったそうだ。
当時24歳だった立石さんの母・初枝さんは、掘り出した土砂を200メートルほど離れた海辺に運ぶのが一番大変だったと話していたという。
板の間にある重い木製の扉を持ち上げると、地下へ続く急傾斜の階段が姿を現す。のぞき込んだ床下は、レンガやコンクリート、頑丈な木で支えられ、湿気を含むカビ臭さを感じた。
階段を下り、砂地に体を横たえて目を閉じた。外部の音は遮断され、自分が唾をのみこむ音が大きく感じられる。この真っ暗な地下壕に身を潜め、迫り来る空襲に備える時間はどんなに心細かっただろうか――と思いを巡らせる。
消えゆく歴史の”証人”
1945年(昭和20年)6月の福岡大空襲では、福博の町が火の海となり、多くの人が防空壕内で熱死したとされる。
安兵衛さんたちは、同年3月の東京大空襲で多くの人が火災の熱によって、壕の中で命を落としたと聞いていた。大浜地区では長老たちの判断で、自宅の防空壕ではなく現在の福岡県庁そばの松林に避難して、助かった人も多かったという。
戦後は地下倉庫として使われていたが、小学生だった立石さんが「悪さ」をすると、父の国男さんに閉じ込められたという。「真っ暗で怖くてね。扉をたたいて泣きわめいていました」。泣き声が近所のおばあちゃんの耳に届くと、父をなだめて助け出してくれていたそうだ。
この防空壕を公開するようになったのは20年前、立石さんが店を引き継いでからだ。バブル期を経て近隣の建物も新しくなり、防空壕が残る家も少なくなっていた。「悲惨な歴史を伝えていかなければ。再び防空壕を使うような時代にしてはいけない」という思いがあった。
小中学生が平和を学ぶ
立石ガクブチ店には、8月になると市内の小中学校から連日のように平和学習の児童生徒が訪れる。大濱流灌頂の日には、祭りにやって来た人も開放された店内で防空壕の話に耳を傾ける。これまでに留学生を含めて1万人ほどの見学を受け入れたそうだ。
取材で訪れた日の午後、写真を飾る額縁を購入するために福岡県篠栗町から足羽百合子さん(82)が来店した。防空壕の存在を娘に聞き、ぜひ見たいと思っていたという。足羽さんは、3歳の頃に疎開先の島根県米子市で体験した思い出を話してくれた。
空襲警報が鳴ると、一斉に防空壕へ走った。足羽さんも防空頭巾をかぶって母親と一緒に逃げ込んだ。中は真っ暗で、隣の人の顔がかすかに分かる程度。「怖くて、怖くて。外の様子を知りたくて隙間からのぞこうとすると、大人に怒られました」。そんな体験がずっと忘れられないという。同行した娘と孫も、静かに話を聞いていた。
ロシアによるウクライナ侵略、さらにパレスチナ自治区・ガザでの戦闘。世界では今もなお、戦禍によって家族が引き離され、尊い命が失われている。
「戦争では戦闘に無関係な市民が苦しめられる。やるせない思い」と立石さん。店の地下壕は、市民生活と戦争が隣り合わせだった時代の痕跡でもある。平和への強い思いを胸に、家族を守るために祖父たちが掘った防空壕の話を伝え続けている。