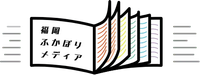夢の欧州大飛行 北九州市の神社に残る「東風号」のプロペラ

西大野八幡神社の拝殿に飾られているプロペラ
記事 INDEX
- 東京からローマを目指す
- 感謝を込めて神社に奉納
- 郷土の人の偉業を知って
北九州市小倉南区の中谷地区にある西大野八幡神社の拝殿に、木製の大きなプロペラが奉納されている。1350年以上の歴史がある神社になぜプロペラが――。背景を探ると、この地で育った河内一彦さんが1世紀前に、プロペラ機「東風(こちかぜ)号」で「欧州大飛行」の偉業を達成し、その感謝の意を込めて奉納したものだった。
東京からローマを目指す
西大野八幡神社は、紫川上流に近い緑ゆたかな山の麓に鎮座している。長さ約3メートル、重さ約30キロの2枚羽根のプロペラは、1925年に日本で初めてシベリア経由でヨーロッパまで飛行した東風号で使われたと伝えられ、当時の写真とともに拝殿の上部に飾られている。
東京から最終目的地のローマまで1万7000キロの飛行距離を、河内さんらを乗せて回り続けた木製のプロペラ。無数の傷跡から、世紀のプロジェクトに携わった人たちの夢や野心が感じられた。「翼よ、あれがパリの灯だ」の名言で知られる、アメリカの飛行士リンドバーグが初の無着陸大西洋単独横断飛行に成功したのは1927年。河内さんらが偉業を達成した2年後のことだった。
河内さんの生家に今も住む、親族の河内正則さん(68)に話を聞いた。1901年に道原(どうばる)の地に生まれた一彦さんは、陸軍航空学校を経て、大阪朝日新聞航空部に入った。当時は昭和天皇のご成婚などもあり、新聞各社で飛行機を使った速報競争が過熱した時代。そんな頃に「欧州大飛行」の計画が持ち上がり、「当時一、二を争う飛行技術だった」という一彦さんに白羽の矢が立った。
とはいえ無線もレーダーもない時代。東京から福岡県の太刀洗、北朝鮮の平壌などを経由して欧州を目指したが、多くの困難が待ち受けていた。シベリアでは、墜落して機体がひっくり返り、村人と一緒に起こし上げた。ラジエーターから液体が漏れ出したため、近くにあった木材を差し込んで応急処置を施した。「再び飛び立つことができる平地があったのでしょうね。運がよかったと思います」と正則さん。トラブルに遭遇するたび、その地で修理を繰り返しては飛行を続けた。
感謝を込めて神社に奉納
生家には、中国・ハルビンで大勢の人に歓迎される写真があり、往時の熱狂を今に伝える。誕生して間もないソビエト連邦の首脳陣と面談した記録も残されているという。飛行したのは日露戦争の20年後。かつての敵国への恨みはみじんも感じさせない熱烈な出迎えを受けたそうだ。
正則さんは「ロシアの大地をしかも低空で、よく飛ばせてくれたな、と思います。国家としてではなく、民間の事業だったから、国も住民もおおらかに受け入れてくれたのでは」と話す。目視が頼りの飛行のため、天候に恵まれた日中などにしか飛べず、夜間は現地での宿泊となる。「南京虫にやられて眠れぬ夜も多かったとも記録されています」
東京を発って4か月後、ローマに到着した東風号。想定外の苦難を乗り越えながらも、目的を達成できた感謝の意を込めて、帰国から数年後、一彦さんはプロペラを郷里の神社に奉納したそうだ。「自分は帰れないから、せめてプロペラだけでも、という思いもあったのでは」と正則さんは推測する。機体は第二次大戦後、GHQ(連合国軍総司令部)に接収され、処分されたという。
郷土の人の偉業を知って
「欧州への飛行は、日本の存在を世界にアピールするために、国の威信をかけた事業でもあった」と正則さん。飛び立つ前には、全国から数万通の励ましの手紙やお守りが古里の道原に届いた。そうした贈り物は、裏山にあった祠(ほこら)で保管していたが、収納できない量に膨らみ、二つの米俵に入れて屋根裏に移していたそうだ。
かつて祠があった場所には記念碑が立ち、その上方に東風号のレリーフが刻まれている。地域を知る学習の一環で、地元の児童たちが時折この碑を訪れ、一彦さんの功績を学び、1世紀前の世界へと思いを巡らせるそうだ。
一彦さんの母校で2008年に閉校した旧道原小学校の職員室には、予備として空旅を共にした、もう一つのプロペラが保管されている。道原地区町内会の松岡洋之前会長(63)は「欧州大飛行を成し遂げた人物が、ここ道原の出身だということを知り、誇りに思ってほしい」と願っている。