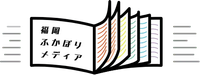大學湯で『飯舘村に帰る』を見た、聞いた 声と色と音が重なり積もる上映会

『飯舘村に帰る』を見る人たち
記事 INDEX
- 青い夕闇につつまれて
- 聞くことは変わること
- 「記憶」が重なり積もる
福岡市東区箱崎の「大學(がく)湯」で6月27日、仙台在住の映像作家・福原悠介さんの作品『飯舘村に帰る』が上映されました。福原さんのトーク、大學湯を運営するアーティスト・銀ソーダさんとの対談、銀ソーダさんととんちピクルスさんによるミニライブなど盛りだくさん。汗をかきつつ見た、聞いた上映会をレポートします。
あわせて読みたい:
大學湯で『飯舘村に帰る』を見る、囲む、聞く 福原悠介さんインタビュー
<『飯舘村に帰る』とは>
東日本大震災による原発事故の影響から、全域が計画的避難区域に指定された福島県飯舘村。2017年3月に避難指示が解除され、仮設住宅で約6年間暮らした住民の一部は帰村。住民たちの語りを聞き手・島津信子さん(みやぎ民話の会)と映像作家・福原悠介さんが記録した2019年の映像作品。
<大學湯とは>
1932年(昭和7年)に創業した銭湯。長らく地域で親しまれるも、老朽化により2012年廃業。創業者の孫である石田健さん(一般社団法人DGY代表理事)とアーティスト・銀ソーダさん(同理事)が中心となってクラウドファンディングで改修資金を集め、2021年にコミュニティースペースとして再出発した。
青い夕闇につつまれて
上映会当日。大學湯を訪れると、銀ソーダさんがいつもの白衣姿で「こんにちは!」と奥のアトリエから顔を出しました。鈍行列車で10日がかりで仙台から福岡へやってきた福原さんは、すっかり箱崎の空気になじんで機材を淡々と整えています。
ミニライブに出演するとんちピクルスさんが、ふらりと腹ごしらえに出かけたかと思えば、アイスクリームを差し入れにくる人も。入れ替わり立ち替わり人が出入りする、銭湯らしいくつろいだ雰囲気が漂っていました。
18時半ごろ、お客さんが並び始めて「夜の大學湯に人が戻ってきました」と銀ソーダさんはうれしそう。浴場と脱衣場だった空間に40人ほどが入り、銭湯時代の大きな扇風機が一台、冷房はありません。
白いタイル壁にしつらえたスクリーンで『飯舘村に帰る』の映写が始まりました。作品には、年老いた人たちが村や生い立ちについて話す姿が記録されています。
「飯舘村ってどんな村ですか」という問いかけに「いい村だぁ。ここがいいんだ。(紅葉が)あかくなった、花咲いたってな」と、こたつで話す声が浴場に響きます。「福島の方言が聞き取れなくても気にしないで」という福原さんのあいさつを思い出しながら、お客さんは語りに耳を傾けている様子です。
上映中、飛行機の音やニャアと猫の声が。大學湯の窓や玄関は開けっぱなしなので、町の生活音が流れ込んできます。この音は語る人の日常か、聞いている私たちの日常か。外と内の境目が曖昧になって、飯舘村と箱崎が交わるような不思議な体感がありました。作品以外の音声は「妨げ」とされる映画館では、起こりえないこと。
銀ソーダさんの作品の青と夕闇が溶けあって、いつしか暑さも和らぎ、飯舘村の人々の語りにより深く引き込まれていくようでした。
聞くことは変わること
上映後、福原さんが自己紹介を始めました。東日本大震災を機に、一度離れていた映像の仕事に再び関わったこと。復興支援企画として花火大会の映像を撮ったとき、自分を含む何台ものカメラが子どものはしゃぐ姿を取り囲む、「グロテスクな光景」にゾッとしたこと。消費されがちな「復興イメージ」を撮ることは、被災した人や土地から奪う行為だと気づいたと話します。
震災後、多くのジャーナリストや映像作家が仙台へ来たものの、被災した土地や人にどうカメラをむけ、話を聞き、記録すべきか「誰も答えを持っていなかった」といいます。福原さんの「道しるべ」となったのは、東北で村人を訪ね歩いて民話を聞く活動を50年以上続けている小野和子さんでした。
民話の「採集」を目的とせず、人を訪ねてただ話を聞く「採訪(さいほう)」という小野さんの姿勢に福原さんは驚きました。村人たちが「みんなほんとうのことだよ」と語る民話を聞くことで、自らの固定観念が壊され、愚かさを知ったという小野さん。「聞くって、こっちが変わらなきゃいけないの」という言葉に、福原さんは「聞くことは変わること」だと気づいたといいます。
タイルの上で体操座りをしてうなずく人、身を乗り出してじっと聞く人。整然とした横並びではなく、思い思いの体勢で福原さんの語りを囲んでいました。
対談では、銀ソーダさんが大學湯とのゆかりを語ります。箱崎に生まれ育ち、幼少期から祖母と母と大學湯に通った銀ソーダさんは「アートを通じて何かできないか。大切な記憶の場所を守りたい」という思いから、創作活動の拠点を置くだけでなく運営にも関わるようになりました。
ふと、銀ソーダさんから以前に聞いた話を思い出しました。「昨年再開したとき、銭湯が復活したと思った近所の人が風呂桶をかかえて来ちゃって」と。それほどに、人々の日常が刻まれた場所。最近では「初めて来たのに懐かしい、心洗われる場所」といわれるそう。「もう湯船にお湯は張れないけど、"創造"の湯で心を洗い流せたら」という願いのもと、大學湯は「公共の場」として息を吹き返したのです。
「この建物自体、記憶が残響する場ですね」と、福原さんは壁画『創造』を見上げます。「疲れを癒した人たちの湯気とか、タイルを流れるお湯とか、見えない記憶を可視化したい。すべてを表現できる"青"で、私はどの作品も"記憶の海"を描いています」と話す銀ソーダさん。「『飯舘村に帰る』も社会問題を問うより、村人たちの記憶によって一つの土地をつかみ取ろうとする作品なので。"記憶"という接点がありますね」と福原さんは語ります。
「私が箱崎をいい町と思うように、飯舘村の人たちもいい村、帰りたい場所と思ってる。同じだなあ」という銀ソーダさんの言葉は、その場にいた人たちの「土地を思う気持ち」に通じたことでしょう。
「記憶」が重なり積もる
会場から感想を募ると、「つらい時間も記憶となることで、片づく、ゆるす感覚が生まれるのかも」とぽつりぽつり話す人。「中学生のころに見た震災のニュースは"画面の向こう"だったけど、この作品は一緒にいて聞いた気持ちがしました」「普通に暮らす人たちが普通に話す、生きている人の姿が見られてよかった」という声も。
「この作品を撮った意図は?」という質問に対し、「"被災した人"を撮るのではなく、ここに長く暮らしてきた人の顔を見せたい、声を聞かせたい。聞き手と語り手の関係性を撮ること以外に、意図はありません」と答える福原さん。「(解釈は)見た人に委ねるということ?」と尋ねられ、「委ねるつもりもないというか……そこに顔や声が厳然とある事実を、受け取ってもらえれば」と慎重に言葉を選びます。
家で1人で見るのではなく、みんなで見て感じたことを語りながら、目や耳が開かれていく感覚。「こうして人が集って場を囲むことも、"聞く"行為になりうる」と福原さんが結びました。
最後にお待ちかね、とんちピクルスさんが「湯船ステージ」に上がり、銀ソーダさんとのライブがスタート。『夜風』の心地よい前奏とともに、銀ソーダさんの筆が動き出します。レゲエナンバー『湯の花』が流れると、やや緊張していた背中がふっとゆるみ、描いている姿は踊っているよう。「ダムの底に沈んでた旅館」の哀愁を描く曲は、この場にぴったり。ラストは、名曲『夢の中でないた』を歌い上げる声と青い絵の具が絶妙の呼吸で響きあいました。
「描いているときは"近づきがたい"って言われるのに、今日の私は真逆でした」「僕のウクレレの"ほわんほわん"効果かな」と笑う2人。「一瞬一瞬が記憶としてこぼれ落ちていくのが怖いから、カタチを残したくなるんですね。のせた絵の具をアクリル板で引っかいたりして」と銀ソーダさんはライブペインティングを振り返ります。
参加者へのアンケートには、一人ひとりの揺さぶられた感情が綴られていました。「私もきっと村に戻ると思う。変えられない生き方を悲しくも愛しくも感じる」「我がことに置き換えて周りの声を聞かなきゃと思うけど、迷う」「自分の意思を入れずに撮るなんてこと本当にできるんだろうか、混乱しています」――。
目の前にある顔を見て、語りを聞き、それぞれに受けとった一夜の上映会。大學湯に響いた声と色と音は湯気のごとく消えたようで、記憶として心の奥底に重なり積もり、時間や場所を行き来しながら思い出されるのかもしれません。
あわせて読みたい:
大學湯で『飯舘村に帰る』を見る、囲む、聞く 福原悠介さんインタビュー